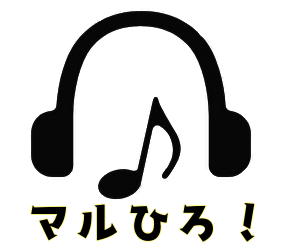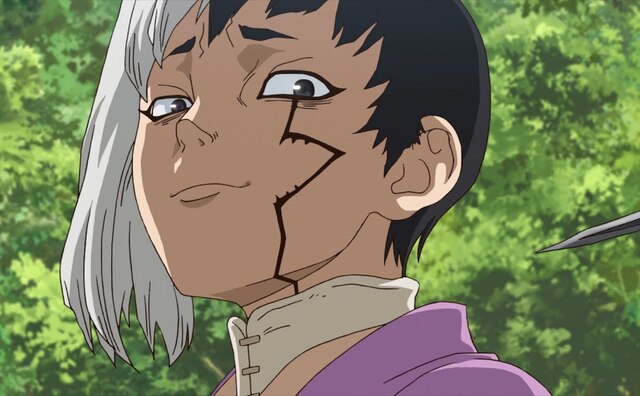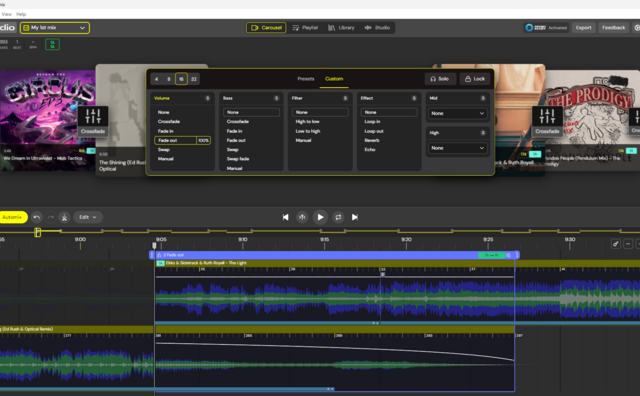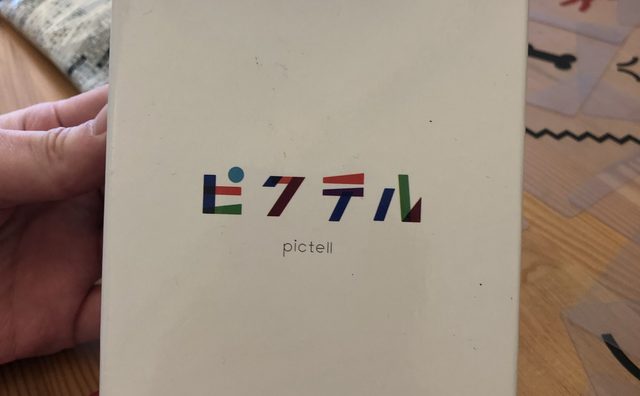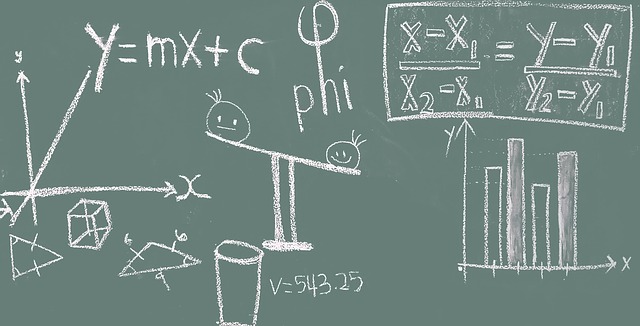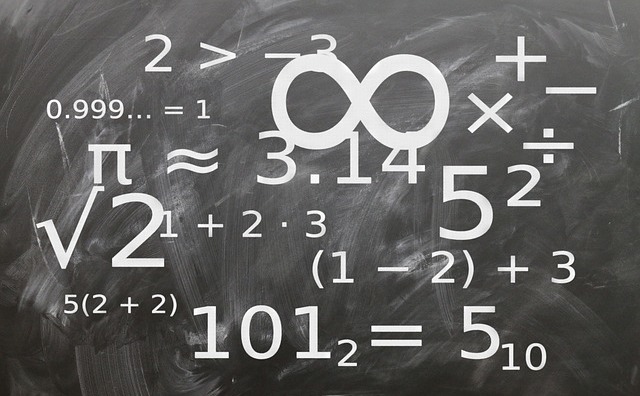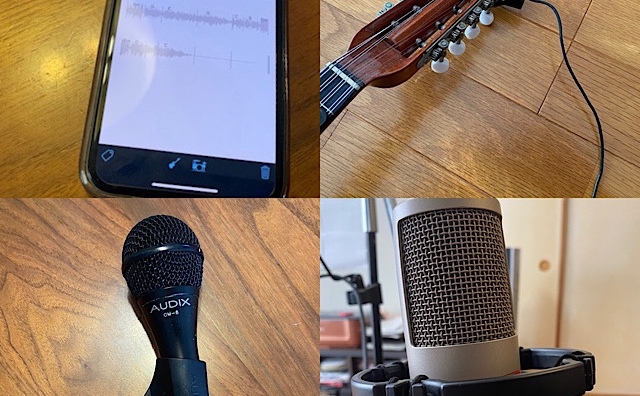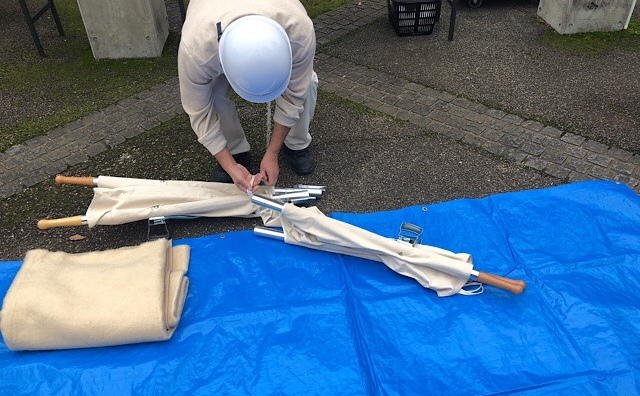ちょっと似ていて迷う「適用」と「適応」。
どちらも「合う」「合わせる」という意味を持っていますが、
実は使う場面がまったく違います。
今回はこの2つの言葉を、例文を交えて整理してみましょう。
【例文】で納得しちゃいましょう
例文①:ルールを○○する
- この規則は、すべての会員に適用されます。
- 彼は新しいルールにすぐ適応した。
👉 「当てはめる」のが“適用”、“慣れる”のが“適応”。
例文②:環境との関係
- このソフトはWindowsにもMacにも適用できる。
- この花は寒い地域にも適応して咲く。
👉 “使えるかどうか”と、“合わせて生きる”の違いです。
例文③:人と仕事の場面で
- この制度を新人にも適用する。
- 新人がすぐ職場に適応する。
👉 “ルールを当てはめる”のか、“環境に慣れる”のかで真逆になりますね。
「適用」と「適応」の意味合い

適用(てきよう)
規則・条件・原則などを、ある対象に当てはめること。
→ イメージは「上から下へ」=制度を人にかぶせるような感覚。
適応(てきおう)
人や物が、環境や状況に合わせて変わること。
→ イメージは「内から外へ」=自分が環境に寄せていく感覚。
固定表現・よくある用例
| シーン | 正しい使い方 | 例文 |
|---|---|---|
| 法律・制度・割引 | 適用 | この制度は学生にも適用されます。 |
| 環境・体質・状況 | 適応 | 新しい職場にすぐ適応した。 |
| 科学・医療分野 | 適応 | 「高地に適応する身体」など。 |
| ソフトウェア・技術 | 適用 | 「このパッチを全端末に適用する」など。 |
むすびに
“適用”はルールや原則を当てはめること。
“適応”は環境や状況に合わせて変わること。
どちらも「合う」「合わせる」という共通点がありますが、
視点の向きが違うだけで、印象は大きく変わります。
仕事でも会話でも、ちょっと意識して使い分けるだけで、
言葉がぐっと正確に、伝わりやすくなりますね。